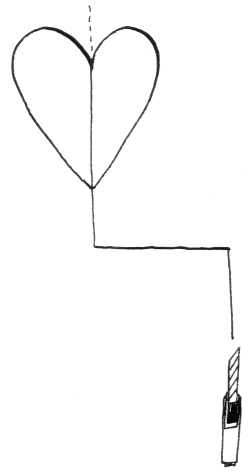
まさに夢のような美しさだったのだ。しんと冷えた教室、長い亜麻色の髪が揺れ、そして赤い色の髪に少し隠れたゴーグルがきらりと光って――、
そうしてそのゴーグルの奥の瞳に思考が行きつくたび、錫也の背筋をぞくりと這い上がるものがあった。今まで感じたことのない、どろりと粘つく、体温よりも低い温度の、それ。
酷く恐ろしくて、だから思い出したくなどなかった、それなのに錫也の脳内で繰り返し繰り返しその映像は問答無用で再生されるのだ。眠りに逃げても、夢の中にまで追いかけてくる。
たまらなく苦しい。呼吸の仕方がわからなくなる。そして猛烈な吐き気。おぞましい何かを喉につっこまれたような感覚があって、その異物を体外に排出したいのだ。それが胃で暴れ続けて、自分が自分でなくなってしまいそうな気がして。
月子に会いたかった。正確には、月子を一目見たかった。あの美しい少女を。
きっとそうすればこんな苦しみは消え去る。いつも彼女はそうなのだ。花が咲くような微笑みで全て消し去ってくれる。錫也は考える必要がない。迷いなんて全部無かったことにしてくれる。
そう、きっと。月子を一目見れれば、あれは白昼夢だったのだとわかるだろう。だって、あんな。あんな表情、月子は浮かべない。よりにもよってあんな気味の悪い男の腕の中で。
ぴるるるる。携帯電話の電子音が、冷え切った静寂をつんざく。
飾り気のない、携帯電話にプリセットの電子音のメロディ。電話帳に登録されていない番号からの着信の場合はその飾り気のない音が鳴る様に設定していた。
電話の主に心当たりはなかった。けれど、不審だとかそんな高レベルの感情を持つには、錫也の心はあまりにも低い温度で凍りついてしまっていた。意識を手放したら二度とこの世界へ戻ってこなくても済みそうなくらい、寒くて、寒くて。
「………もしもし」
ぷつ、とボタンを押して電話を耳に当てる。途端、低く押し殺したような、笑い声が鼓膜をざわりと撫でた。
『やあ、ナイト君。君が自分のお姫様だと思ってたものが無情にも俺を選んでたんだって、ようやく気付けた?』
既に星は凍りついていた
(2012.02.12)
(勇仁ちゃんの「落下星」の続き)
