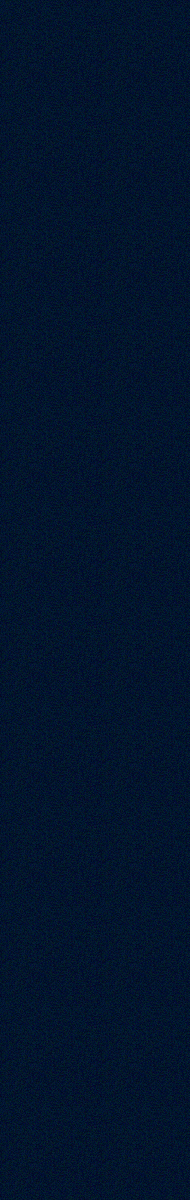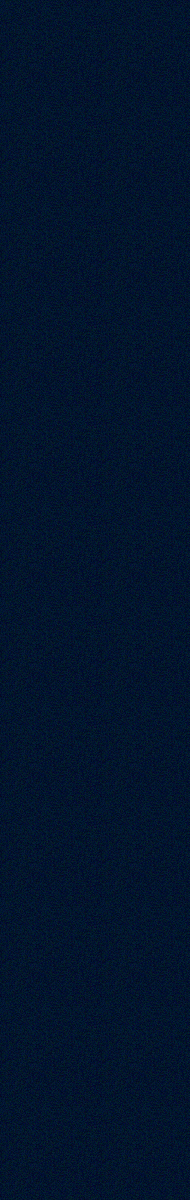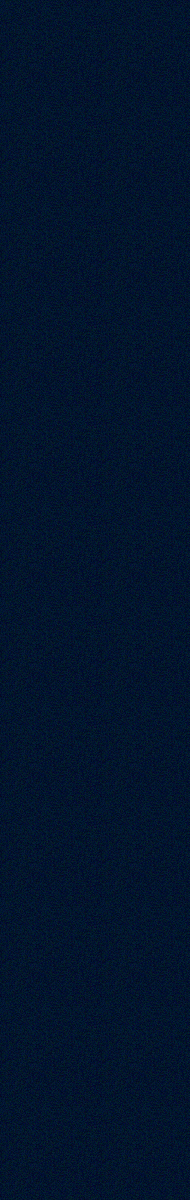
「ああ…」
俺はなんだか、どんな顔をしたらいいのかわからなかった。黒木は話を続けた。
「彼女は儲けた金でイタリアに行ってしまいました。僕には、難病の子供を救うため、クロスワードを教えに行くと
言っていましたが。それで彼女との関係は終わり───その次僕は、真実をこっそり教えてくれた彼女の
友人と付き合うことにしました」
それでやっと、まともな恋愛ができたわけか。良かったな…
「でも、ひと月持ったかどうか。その人は奉仕の精神に溢れた女性で、僕の孤独を理解し、
慰めようと常に懸命になる人でしたが、不幸な男に異様な執着を持つ人でもありました。
不幸であればあるほど恋が燃えるという…でも付き合ってみると案外僕はふしあわせじゃないので、
飽きられて、捨てられました」
「はあ…あは、あははは」
俺は乾いた声で笑った。
「そんな感じで、大学時代では二十人ほどしかお付き合いできませんでしたね」
「はははは……そりゃああんた、世間で言うところのやりチンだよ。あはははは」
もう訳わかんねえや。この人。あーあ。
「僕はつくづく恋愛に不向きな男だと、思い知りました…そんな感じで、暫くは女性とも、恋とも遠ざかっていたんですが。
そこへ現れたのが、御陵君でした。御陵君はほんとに…僕にとっては、如来様のような存在ですよ…彼は僕の全ての欲求を満たしてくれます」
黒木の顔がほんのり桃色になっていく。頭の中で卑猥な妄想が始まったらしい。
「ところで…キフネさんは?どうなんですか、あっちの方は。あ、いや、恋愛は」
「俺…?俺は」
つい歯切れが悪い返事をする。手持ち無沙汰で水鉄砲なんて始めてしまう。
振られるとは思ったが、あまり話したくない。
「───去年の9月まで、居たけど」
「捨てられたんですか」
「う…まあ」
濁る俺に、黒木が肩を寄せてきた。俺はそれをかわしながら、「学生の時から付き合って…ずっと半分?同棲、してた、ん、だけど」
話しながら、その当時の記憶が鮮明に蘇っていった。
彼女は俺より4つ年上で、知り合った時から雑貨屋でバリバリ働いていた。俺は学生だったから、社会人の彼女の感覚と自分の感覚の食い違いは付き合い始めの頃からあったし、しょっちゅう喧嘩の種にもなった。
でも、それでもうまくいってたんだ。何せ三年も続いたし、俺だってその中でちゃんと就職できた。
サラリーマンになった最初の夏。俺は思い切って彼女に結婚を申し込んだ。
いずれ正式に、というつもりで、初ボーナスで婚約指輪まで買った。でも…
彼女の返事は「受け取れない」だった。そこで初めて告げられたのは、彼女の、俺への気持ちが醒めたことと、ずっと前から勤め先のオーナーと真剣な関係を続けてきた、という衝撃の内容だった。
「真剣な関係ってなんですかぁ?」
黒木が訊ねる。
「知るかよ…ま、彼女はずっと───店のメインバイヤーになって海外を飛び回るのが夢だったからさ。オーナーと結婚することで自分の夢も叶ったわけで。結果的によかったのかもしれないけど……彼女自身の幸せのため?ってやつ」
言いながら、こんな風に普通に話せるのが不思議だった。彼女が去った頃、俺は眠れないし飯も食えないって位、鬱になっていたもんだ。ああ、しかし、女って。恋って。俺だって、俺だって、結婚したかったのに〜!
「はっはーん。それでキフネさん、男色の道に?」
「だからホモじゃねえって!!!」
俺は黒木の寝ぼけ眼を睨みつけて怒鳴った。
「でもまぁ、いいじゃんじゃないですかぁ?その女性とは良いお付き合いで終わったんですから。その経験を活かしていけば、キフネさんも今後はよりよいご縁とめぐり合うことでしょう」
お、なんだ?結構いいこと言うじゃん黒木。
「それって何、もしかして黒木さんの霊能力?俺の未来がわかるとか?」
「いや、鏡リュ○ジがどこかで言ってたんですけど」
なんっだ、それ!!?
「………あああ、もう…俺、先にあがるわ…」
言って、俺は立ち上がろうとした。
「あれ?」
何か変だ。腰が抜けたような。うまく立てない。なんでだ?俺が湯の中でもぞもぞしているのに、黒木が気づく。
「どうしたんですか」
「………なんか、おかしい。立てない……?」
黒木が横で見守る中、俺は両手で岩につかまり、自分の体を引き上げた。「…っしょ───うわっ!」
ばっしゃん!!
俺は湯の中に落っこちてしまった。ぷは、と顔を上げる。そこで、初めて気がついた。
全身が燃えるように熱い。浸かっているお湯よりも高熱に感じるほどだ。やばい。のぼせてしまった…その自覚とともに、視界もぐるぐる回りだす。