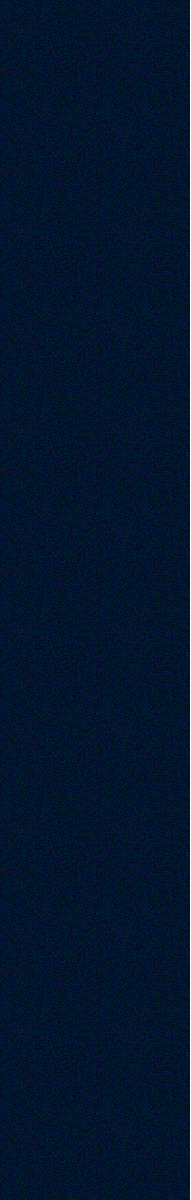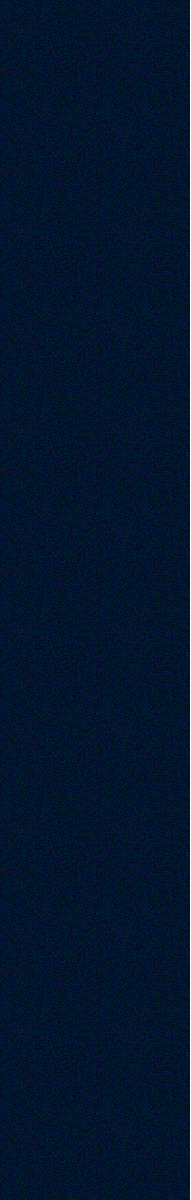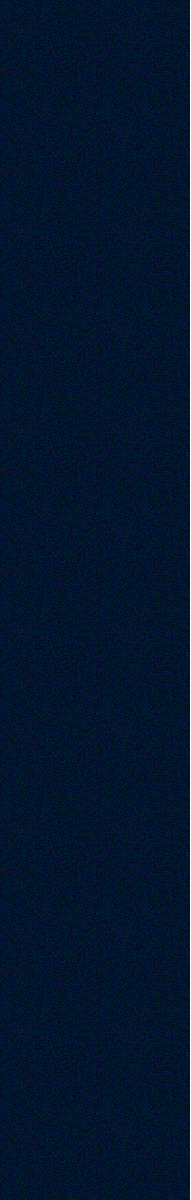
ドンドコ ドンドコ ドンドコ ドンドコ…
どこかで太鼓が鳴っている。
夢とも幻とも見分けがつかない意識の中、俺は目を醒ました。というか、なんで寝てたんだ俺。
ぼんやりと記憶を手繰り寄せる途中、
「あでっ」
突然首の辺りに激痛が走った。
「痛ぇ〜〜…何だよこれ……え〜〜?」
痛みと共に蘇る記憶。
───つまり、さっき部屋で出会った天狗に後頭部を殴られ、気絶させられたってことか?
いやあれは本物の天狗なんかじゃない。冷静に考えてみて、そんなの居るわけない。
やり場のない憤りが沸いてきて、俺は瞼を開けた。
「何だこりゃ!!」
思わず叫んだ。
俺の視界に拡がっていたのは、ペンションの中ではなかった。だだっ広い、総板張りの道場のような空間。その、ど真ん中に一段高く、祭壇のようなものが作られ、高さ三メートルはあろうかという巨大な樽がそびえ立っている。目が慣れてくると、樽の周りに人影を見つけることができた。
人影は、全員全裸に褌、顔に天狗の面をつけた男達だった。4・5人は居るだろうか、男達は俺の方にまったく注意を向ける素振りもなく、ただ黙々と作業に徹していた。汗が滲む肌が、蝋燭の炎に照らされて反射している。
一体、何をやってるんだ?
俺は起き上がろうとして、そこで初めて自分の体に起こっていることを知った。
縛られている。後ろ手に。そして折り曲げた両足首にも、縄がガッチリ絞められている。
力を込めても足掻いても、ビクともしない。
………どういうこと?!!
「お目覚めですか、お・姫・様」
もがいている俺の耳に、含み笑いと共に影が忍び寄ってきた。不自由な身体を動かして首だけ振り返る。
「大河内さん……」
「手荒な真似をして、すみませんでしたねぇ」
「あ・アンタ、一体!?何なんですか、これ」
「儀式なんですよ。これから……貴方は我々の儀式の生贄となるのです」
「!!!!」
生贄?!
何を言ってるんだこのオヤジ?正気か?いや、正気なわけないよ。初めから。冗談が服着て歩いてるオヤジだもん。
しかし俺の思惑とは裏腹に、転がっている俺の周りには、天狗面の男達がじわじわ集まってきていた。
「えっ、ちょ、何ですかあんた達?!うわっ」
あっという間に天狗男に囲まれた俺は、伸びてきた数本の腕に抱えられてしまった。
担がれ、そのままどこかへ運ばれる俺の後を、大河内がついて来る。
「やめろ!!お、お、お、俺に何をする気だ!!??」
「言ったでしょう。貴方は生贄になるんですよ」
「いけにえ?!殺すのか?俺を、殺すのか?!!」
「殺す?…………まさか。ふふふふふふふふふ」
俺の身体は巨大な樽の真下で降ろされた。転がされたのは、一枚の布団の上。その周りには、毒々しい赤やピンク、紫色をしたチューブや瓶、怪しげな器具が並べられ、何故か洗面器が置かれていた。何のために使うものなのか…その答えは、目の前の器具に気がついたことでわかった。
男性器を模した形に、スイッチ、電源コード。これは…紛れもなく……
「先程、あなた方に振舞った吟醸うらすぎ……実は製法に秘密がありましてねぇ。原材料は一般的な吟醸酒と同じなんですが、製造の過程で、特別な、あるものを投入するんですよ…さあ問題。
そのある物とは、な〜んだ?!!」
…………。
場が、一気に凍りついた。けれども大河内は意に返さず、話を続けた。
「今年はその、ある物が深刻に不足しておりましてね。しかし“うらすぎ”は長年村を安定させてきた唯一の財源。生産量を減らすわけにもいかず、ほとほと困った我々は、思い至ったというわけです。そうだ、外部の人間の手を借りようと。───ですが、ものがもの。その上これは重大な企業秘密でもありますから、適当にやるわけにもいきません。協力を得る人材に、この人ならという信頼がなくては到底任せられない。それで色々四苦八苦していたところに現れたのが、キフネさん。貴方だったというわけです」
「は…?」
え〜〜、言ってる意味が全然わからないんですけど。
「協力、してくれますよね?」
ずい、と大河内の顔面が俺に近付く。天狗男達も俺を囲み、密度を増していく。
「協力って…?俺に何をしろって言うんすか……」
にじり寄る男達から逃れようとする俺の耳に、太鼓の音が鳴る。ドンドコ ドンドコ ドンドコ ドンドコ…
「吟醸うらすぎの秘密の成分…」
天狗男の一人が、面の奥から囁く。
「それは…」
「男の」
「 精 液 」
俺は背筋が総毛立った。
「この村も老齢化が進んだ上、若者は皆都会に出てしまったものですからねぇ…人手不足なんですよぉ……」
せ・せ・精液が、酒の、中に…?……俺達がさっき……一升を二本空けた酒が……
「うごぷ」
俺はせり上がる吐き気を抑えられなかった。確かにこれは、企業秘密にしないと、買い手がいなくなるわな……って冷静に感心している場合じゃない。
褌姿の天狗男達が俺を布団の上に組み敷こうと、手を伸ばしてきたのだ。