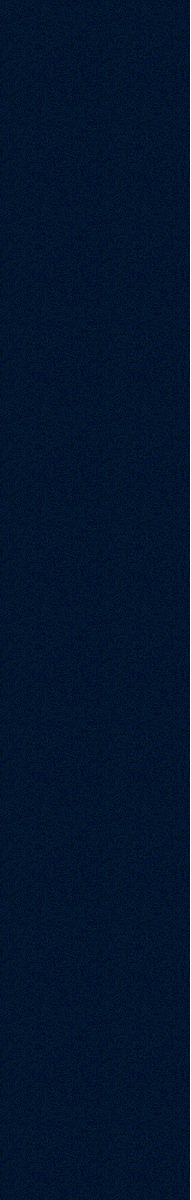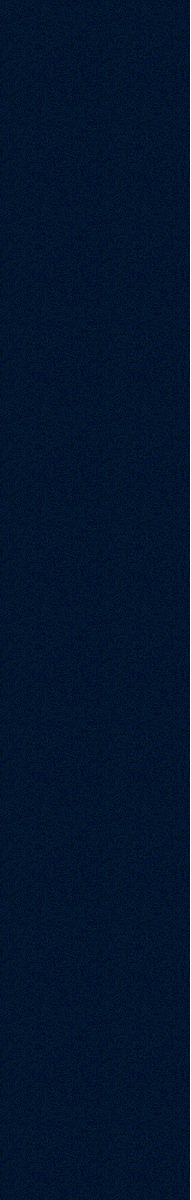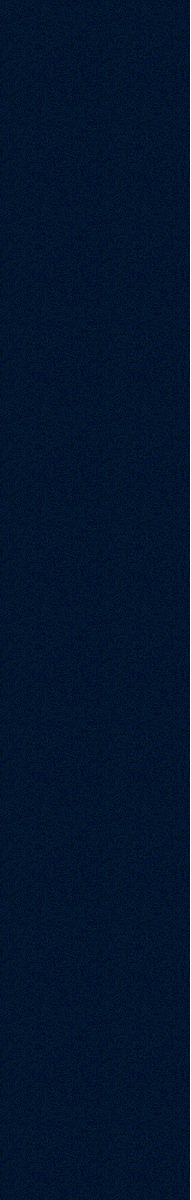
「黒木、ごめんな───俺、お前のこと、騙してた」
(御陵くん!!!)
僕は、目の前にいる愛しい愛しい、この世で一番、これ以上はないというほど愛しい御陵くんの口から淡々と紡ぎ出される言葉を、まるで死刑宣告のように、受け止めていました。
ああ、御陵くん!そんな事、言わないで!
そんな顔、しないで!
僕は!僕には、御陵くんに謝られることなんか、何もないから!!
僕の胸中にはそんな思いが幾千も、嵐のように吹き荒れていましたが、どれ1つとして、現実の言葉になることはありませんでした。
何故?
どうして、なんでしょうか?自分でもよくわかりません。
何か言ってあげたい、心の底からそう思うのに…。
御陵くんは僕の反応を待っています。僕の言葉を。
でも…
……果たして僕は、何か言うべきなんでしょうか?
御陵くんが消えて、僕は半身を失ったかのような喪失と、孤独を味わいました。けれども御陵くんに対して怒りを感じたことは、一瞬たりともありませんでした。傷付けられたという感覚もありません。ただ、身の安全を心配していただけだったんです…突然、ごめん、だなんて謝られると、反対に僕が責められているような気分です。御陵くんに責められるのははっきり言って快感ではありますが…これは、ちょっと。
「今まで、どこにいたの?」
長い間を置いた後、ふと僕の口をついた言葉はそれでした。言ってから、後悔しました。これじゃあまるで御陵くんを追及しているようではないですか!
違うのに…本当に言いたいのは違うのに。僕は、御陵くんを疑っているんでしょうか?心の奥底で?
確かに御陵くんの最後の<騙してた>は、気になるところでした。一体何を?それは、僕に対して、なんですか?
「家。俺の…」
御陵くんは低く、しかしはっきりとそう言いました。
「家?」
僕は驚きました。御陵くんと出会ったのは、この県にあった宗教団体の施設でした。そこに行っていたというのでしょうか?いや、そんな筈はありません。何故なら僕が御陵くんを連れ出したその日、その施設では同時に大捕物があり、以来閉鎖され、今は誰も入れないと聞いていました。
それとも御陵くんの、生家という意味でしょうか?───それなら、僕にとって非常にショックな事実になります。
御陵くんは、僕に一度も、自分のことを話したことがありませんでした。
僕自身に御陵くんの素性に興味がなかった、というわけではありません。それとなく訊ねたことは何度かありました。けれどもその度にはぐらかされて───結局、知ろうとするのをあきらめたのでした。御陵くんが何処から来て、どう生きてこようと、今は僕の傍にいる。それだけを現実として受け止めたら、あとはどうでもよくなったんです。
御陵くんは自由奔放で、何物にも捕らわれない性格です。
そんな人ですから、両親や家庭といったものは、きっと無用に思っているのだろう──そう、思っていました。
「オレさ」
御陵くんは溜息を吐きながら、髪をぐしゃぐしゃと掻き回してから僕を見ました。言うべき言葉が見つからないのは、彼も同じようでした。
「お前んとこ、出てくから」
「………え」
僕は目の前が真っ白になりました。御陵くん、何、言ってるの?
けれども御陵くんの態度は、下手な突っ込みを断固として受け止めない──もとい、真剣そのものでした。
「だから、さよなら」
「……………ど、どどどうして?…僕のことが…嫌いに、なった……?」
「………周が、いるから」
御陵くんと一緒に現れた人のことでした。かの宗教団体の元関係者です。見た目は闇金業者のような悪党です。
御陵くんの精神衛生に大変悪影響な人物です。
「御陵くんは僕より、その人のことが好きなの?」
唾を飲み込み、落ち着きを取り戻してからさらに聞き返すと、御陵くんは顔を上げました。
「ああ」
何ですかその笑顔は!!
……聞くんじゃなかった。僕は地面に伏したくなりました。「嘘だ…」
「嘘じゃない。オレは」
「だって…御陵くん、僕のこと、あんなに好きだったじゃないですか〜〜あんなに、泣いて喜んでたのに。気持ちいいことも、痛いことも、沢山してあげたのに。どうして?…」
「周の方がいい」
!!!!!!!!
「あ……&%=………」
衝撃の余り、僕は言語を喋れなくなりました。しかし、御陵くんは容赦ありません。
「お前のやり方じゃ、オレは本当に熱くはなれない。いつか飽きて……それでダメになる。今以上を欲しなくなる。欲しなくなったら、オレは後悔する。今までのオレを後悔して……いつか狂う。オレはオレじゃなくなる。そうなったオレをきっとお前は…受け止められない」
「受け止めます」