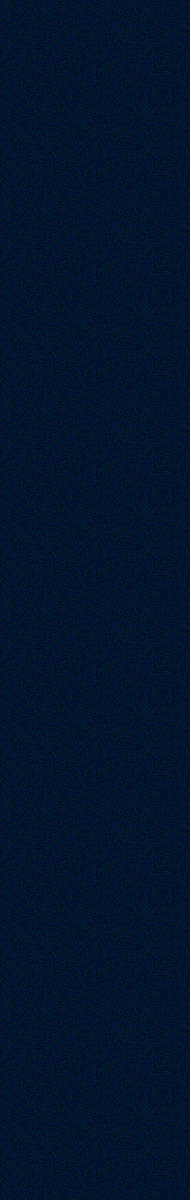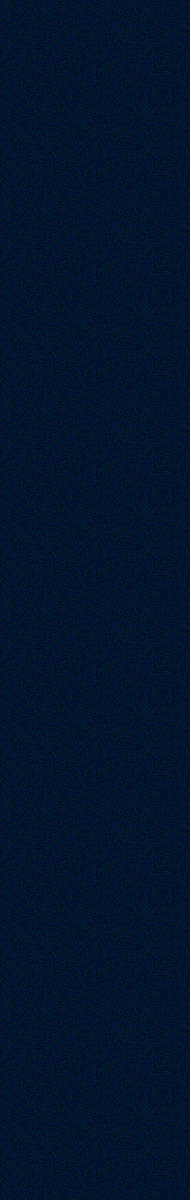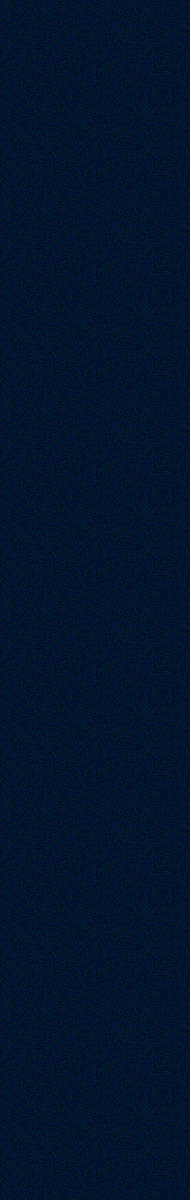
そこは黒木佛具店、と達筆な筆文字で書かれた木の看板が目印の、しなびた駅前商店街にある古い古い仏具屋。 そして時刻は夕闇を過ぎた頃───
「責任は・とって下さらないとねぇ」
天井から放物線を描くように降りてくるその声は、さっきから所在なさげに厚底の眼鏡を指先で上げ下げしている僕の父に向けられていました。
父はずっと苦い顔で、声の主である御夫人と対峙していました。
御夫人は樽のような体に巨大なプレーリードッグがプリントされたシャツと豹柄のスパッツを穿き、左手にはヴィトンのバッグ、右手には愛息子の手をひいて、父との間合いを一歩も退く気配がありません。愛息子は母の手にぶらさがるように、やはり樽のような体を落ち着きなく揺らしていますが、たまに漏らす言葉といえば、お腹がすいただのもう帰ろうだのという類でした。僕は店のカウンターの中に立っていましたが、御夫人と父の間に割り込むことができず、じっと見守ることしか出来ませんでした。
父は黙って御夫人の言葉に耳を傾けていましたが、やっと口を開く気になったようです。
「…どうも、申し訳ありませんでした」
御夫人の表情はみるみる一変し、仁王さまのように怒り出します。
「あなた。さっきからそればかりじゃないですか?私の話、聞いてたんですか?」
「え?あ・はい。すいません」
父はその勢いに面食らって、取り繕おうと頭をへこへこ下げます。夫人は業を煮やして、父に詰め寄ってきました。
「うちの坊ちゃんはね、あなたの息子に虐待されたんですよ?これはいじめなんかじゃありません。ぎゃ・く・た・い。虐待ですよこれは。見て御覧なさい、これ」
「痛いよ、マミー」
夫人は傍らの息子の肉付きのよい腕を引っ張り上げ、父の目の前に突き出します。
まるまるとした腕の表面には、たくさんの蚯蚓腫れのような赤い筋が走っていました。
「これ。腕だけじゃないんです。全身ですよ、全身、赤いシマシマだらけなんです。こんなにひどい傷!一生残ってしまいますよこれは」
父は度の強い眼鏡を吊り上げながら、まじまじと太った子供の腕を見ました。
そして僕のほうをちらりと見て、上目遣いに夫人に尋ねました。
「本当に、うちの柳介が?」
「ですから!最初からそう言ってるじゃありませんか!!ねえ坊ちゃん?」
「───柳介。そうなのか?」
そこで父は初めて僕を振り返りました。父だけでなく、夫人、その息子までの視線が僕に集まります。僕はカウンターに寄りかかっている体勢を直立に戻しました。
「えーと」
僕は記憶を巡らせて、説明しました。
「きょうの帰りに、ゲームセンターの前で彼にお金を貸してくれって、言われたんです」
夫人の顔面は凍りつき、太った息子は僕の顔を睨みつけました。
「なんですって?」
「それで僕は持ってませんって言いました。そしたら、てめえなめんなよって皆で僕の腕を引っ張ったものですから」
「それで、殴ったのか?」
父が言います。昔から、状況把握には少々ぞんざいな父でした。
「いいえ。逃げました」
「まあまあまあまあ」
御夫人は南国の鳥のような声を出しました。
「なんてひどい。うちの坊ちゃんを虐待した挙句、恐喝の疑いまでかけるの?一体どういう育て方をされてきたんでしょうね?こういう子は将来絶対出世しないのよ。そうよ。犯罪者。犯罪者になるのよこういう子は。よく見れば子供のくせに鄙びた目をしてる。腐った魚みたいだわ。間違いないわ。おお、怖い」
ベラベラとまくしたてて僕と父を圧倒した御夫人は、ほう、と一呼吸置きました。
「いいわ。こうなったら、法廷で戦いましょう。裁判を起こして、それでおたくから賠償金をがっぽり頂きますからね。それじゃあ。行きましょ、坊ちゃん」
「ちょ、ちょっと。待って下さいよ奥さん」
立ち去ろうとする御夫人とでぶの子供に、父が慌てて追いつこうとしたその時でした。
どすん、という音がしたかと思ったら、踵を返したはずの御夫人が後ろ向きによろめいていました。
「あ、あ、あなた、なんですか。いきなり」
御夫人の前にはいつのまにか誰かが立っていて、体がぶつかったにも関わらず平然としていました。
「───茨信(しのぶ)さん!」
僕は思わず叫んでいました。
「やあ。こんばんは、柳介君。藤一郎さん」
茨信さんは御夫人の頭の向こう側で、白い顔に微笑を浮かべて僕に言いました。
茨信さん、とは父の父、つまり僕の祖父の兄の三男にあたる人で、山奥の本家に住んでいるのですが、たまにこうして訪ねて来てくれます。れっきとした男性ですが、全体的にほっそりとして白く、美人で評判だった祖母の家系ゆずりの目鼻立ちに、とても澄んだ飴色の目をしていて、見ているだけですっと引き込まれるような魅力を持った人でした。
年齢は、父より少し下か、同世代か───四十歳はとうに迎えているはずでしたが、しかしどう見ても、二十歳そこそこ、あるいは十八歳くらいにしか見えませんでした。
「どうしたんですか、急に?またお仕事?」
僕はカウンターを抜けて茨信さんの下に駆け寄っていきました。茨信さんは近付いてきた僕の頭を撫でて笑いかけてきました。それがなんとも魅力的で、僕はつい顔が紅潮してしまいます。
「柳介君に会いに来たんだ」
澄んだ声で言われて、僕は顔の熱が頭の中まで充満するような気持ちになりました。
「ぼ、僕にですか」
「うん。大事な話があるんだ。今から私と一緒に来てくれるかい?」
茨信さんの誘いを僕が断る理由はありません。もう夢中で頷いて、僕は茨信さんと店を出ようとしました。